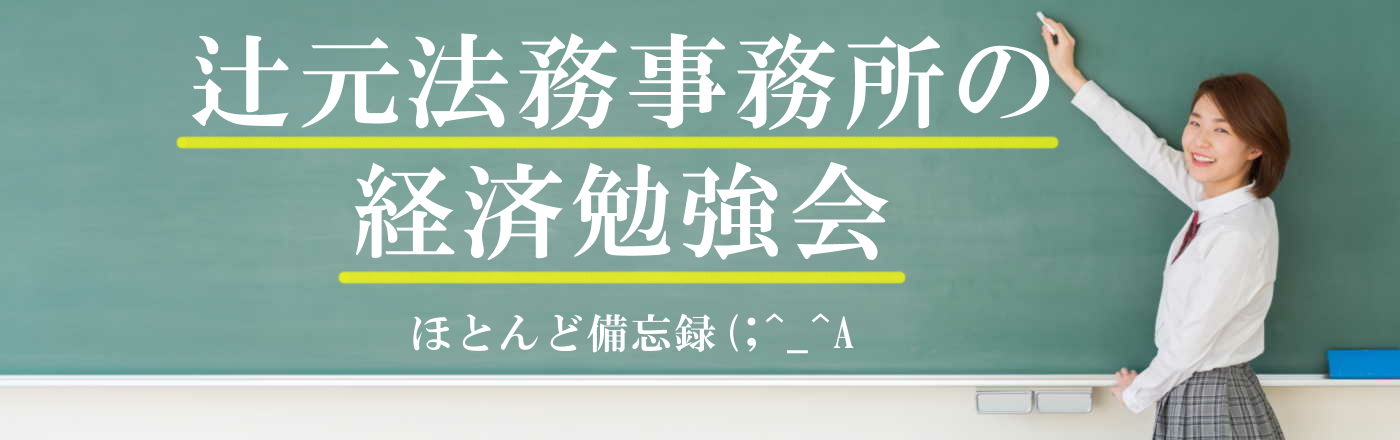
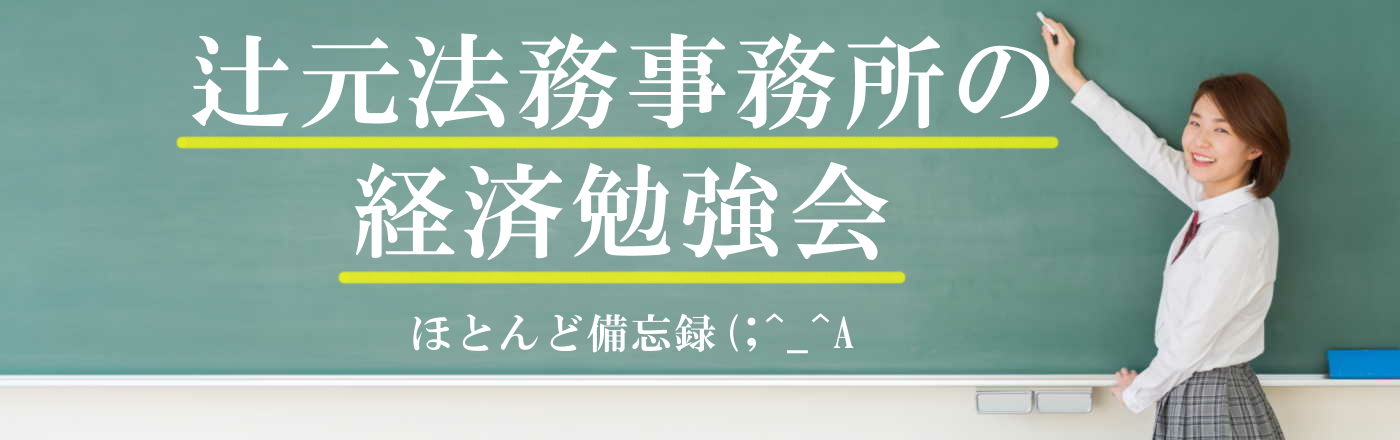
接続詞を極める
接続詞と語彙力を極めると、文章が伝わりやすく、読みやすくなります。
.png)
このサイトでは接続詞を、論理の接続詞、整理の接続詞、理解の接続詞、展開の接続詞の4類に分けて、その働きの違いを順に説明します。
論理の接続詞
代表例=したがって/ところが/そのため
論理の接続詞は、論理の条件関係です。 論理の接続詞があると、因果関係が明確になり、文章の流れが論理的になります。そのため、書き手が自分の意見を説得的に述べたい場合によく使われます。
整理の接続詞
代表例=また/一方/または
整理の接続詞は、同類のものを並べる加算関係です。整理の接続詞があると、長くて複雑な内容も整理され、文章が読みやすくなります。そのため、入り組んだ話題を誤解なく述べたい場合によく使われます。
理解の接続詞
代表例=すなわち/たとえば/ただし
理解の接続詞は、足りない情報を補う補充関係です。理解の接続詞があると、読み手の疑問が解消され、文章の理解が深まります。そのため、書き手と読み手の知識の差を埋めたい場合によく使われます。
展開の接続詞
代表例=さて/このように/いずれにしても
展開の接続詞は、話題の展開です。 展開の接続詞があると、局部的な理解にとらわれずに文脈が捉えられ、書き手の意図がつかめます。そのため、長い文章で文章の全体構造を示したい場合によく使われます。
それでは、解説していきましょう。
連続してしまう「また」
カテゴリー[整理/並列/添加]
似た内容のものを後から加える
何らかを文章の中で列挙しようとすると、並列の接続詞である「また」を使うことが一般的ですが、これが連続すると幼稚に見えてしまいます。
対策1:第一に〇〇、第二に〇〇、第三に〇〇…
対策2:まず〇〇、つぎに〇〇、さらに〇〇、そして〇〇、同様に〇〇…
連続してしまう「次に」
カテゴリー[整理/列挙/序列]
順序性の有無を問わず順序を付けて列挙する
何らかの順序を文章の中で列挙しようとすると、序列の接続詞である「次に」を使うことが一般的ですが、これが連続すると幼稚に見えてしまいます。
対策1:最初に〇〇、次に〇〇、続いて〇〇、最後に〇〇…
対策2:まず〇〇、つぎに〇〇、さらに〇〇、そして〇〇…
賢い人が使う「他方」
カテゴリー[整理/対比/他面]
二つのものを対照し異なる見方を示す
異なる見方を対にして示す接続詞のなかで、頻度が高いのが「一方」で、長い文章を書くときに欠かせない存在です。段落と段落など、比較的長い単位をつなぐ傾向があるからです。その意味で並列の接続詞の「また」と似ており、長い記述を並べるとき、類似点を強調するなら「また」が、相違点を強調するなら 「一方」が用いられます。
「他方」は、「一方」よりもさらに対立色が薄いものです。もう一方の見方というより、単に別の見方を示すにすぎず、「さて」「ところで」のような転換に近いものもあります。
私が使う「一方」はさほど強くなく「ところで」程度なので、最近は「他方」に換えていますし、賢い人(評論家M氏)は「他方」を多用し、「一方」はめったに使わないことに疑問を持っていました。
失敗が多い「なお」
カテゴリー[理解/補足/付加]
前に述べた内容の関連情報を追加・修正する
そのあとに、まとまった先行文脈の内容を補足修正する内容を続けることで、先行文脈の内容を微調整し、より正確なメッセージを読み手に伝えようとするものです。「なお」の場合は、一言断っておくという感じで、先行文脈を変更する程度は、「ただし」ほど強くありません。補足の際は、「なお」と「ただし」を両方音読してみるとよいでしょう。
または、もしくは、あるいは
カテゴリー[整理/対比/選択]
可能性のある選択肢を並立する
前件と後件について、「または」は対称性が高い、すなわち対等の似た内容を並べるときに使います。「もしくは」も似ていますが、前件がメインで後件がサブという関係になります。
この両者は特に使い分けなくても読みにくいことはありませんが、「あるいは」は少し違和感があるかと思います。
「あるいは」については、複数の候補があって、いずれとも決めがたい場合に、その候補に使います。
困ったら同義語で雰囲気を変えてみる
帰結の接続詞は、エンジニア系の報告書で「〇〇によって〇〇になる。よって〇〇となる。」のように連続することがあります。前項のような応用までのものではないとき、単に同義語に置き換えて連続の単調性を回避してみると、読みやすくなります。
更正前:〇〇によって〇〇になる。よって〇〇となり、よって〇〇となった。
更正後:〇〇によって〇〇になる。したがって〇〇となり、それゆえ〇〇となった。
相手により使い分ける
例えば金融機関への報告書であれば、専門用語を使った方がお互いの理解が深まりますが、経済の専門ではない取引先への報告書であれば、専門用語を使わずに、分かり易く書いてあげたほうがよいでしょう。
でも、いくら金融機関へでも、やりすぎは「アザトク」見られますので、要注意ですね。